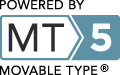県立茅ケ崎北陵(7)
■厳しい練習・失意の大会、後に開花
女子フットサルの元日本代表主将の藤田安澄(あずみ)(40、1997年卒)は高校時代、バスケットボール部の主力だった。地区大会で上位に入って県大会に出るという目標があり、練習は厳しかった。
ただ部活の指導方法には疑問を感じた。チームを鼓舞するためか、頻繁に叱られたり、きつい反復練習をやらされたりした。生徒が目的意識を持ち、自分たちのアイデアでやれたら、もっと良いプレーや試合ができたと思う。
当時のチームメートはいまも仲がよく、たまに茅ケ崎市内の体育館に集まり、ゲームを楽しんでいる。
筑波大学に進み、バスケを続けてレギュラーを目指した。思うような結果が出ず女子サッカー部に転向。主力としてインカレ(全国大会)に出場した。フットサルに出会ったのは通信制高校で保健体育を教えていた時。1チーム5人で、全員で攻めて守る競技はバスケと似たところがあり、自分に合っていた。都内のクラブチームで活躍し、2007~10年に日本代表に選ばれ3大会で主将を務めた。
引退後はブラインドサッカー女子日本代表のコーチを務めるほか、湘南地域で子どもから大人まで指導するフットサルクラブの代表となった。「何がいけないか理由を明確に伝え、納得して練習やプレーをしてもらうように心がけています」
1993年の箱根駅伝で優勝した早稲田大学のアンカー、富田雄也(かつや)(48、1989年卒)は高校時代は陸上部員。3年の時、県大会の3千メートル障害で2位になり、インターハイ出場を目指して関東大会に臨んだ。
しかし大会直前、体育の授業中に足首をねんざし、治りきらずに惨敗。失意の中、高校での競技を終えた。国立大学志望だったが、共通1次試験の結果が思わしくなく浪人を覚悟した。
担任の言葉が、人生を変えた。「どこでもいいから、一つ合格してから浪人しろ」
少しでも自信を持って翌年、第1志望校に挑め、という担任の意図だった。富田は「ダメもと」で受験した早稲田大学に合格。本格的な競技は高校までと決めていたが、父親に「陸上部(競走部)に入らないと学費は出さん」と言われた。「それなら、もう少しやってみるか」といった程度の気持ちで競走部に入部した。
厳しい練習を続け、1年生から良い成績を出せた。正選手のけがや体調不良もあり、箱根駅伝のアンカーに抜擢(ばってき)された。チームは9位。翌年もアンカーを務めた。
安定した走りが特徴で、4年時も最終10区を任された。スーパールーキーといわれた渡辺康幸らが入ったこともあり、チームは久々に箱根駅伝総合優勝を果たした。ゴール数キロ前に優勝を確信すると、摂生を怠ってメンバーから外された前年の悔しさなどを思い起こし、感情がこみ上げた。テープを切った瞬間は、興奮で記憶にないという。
早稲田のアンカーは卒業後、茅ケ崎市役所に入り、現在は市民自治推進課長をしている。
◇
県立茅ケ崎北陵高校は今回で終了します。(遠藤雄二)